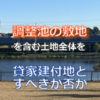建物が滅失しても借地権は滅失しないとした事例

建物が滅失しても借地権は滅失せず、本件贈与時に本件土地に借地権が存在することは明らかだとして、請求人の主張が認められた事例 平成26年5月9日裁決・沖縄
争点
本件土地の価額は、借地権の価額を控除して評価すべきか否か
請求人の主張
本件土地の価額は、借地権の価額を控除して評価すべきである。
借地法第2条第1項は、建物が朽廃した場合を除き、借地上の建物が取壊しなどにより滅失しても借地権は消滅しないと解されている。
借地権の及ぶ範囲は、建築面積 (庇を含む。)のみに限定されるものではなく、契約内容、土地の使用制限等の事実関係に基づき判定されることから、本件贈与時に本件土地には、 借地権は存する。
原処分庁の主張
本件土地の価額は、借地権の価額を控除して評価すべきではない。
本件建物は、借地法第2条第1項に規定する非堅固な建物で借地権の存続期間は30年であることからすれば、本件贈与時は建築から32年経過しており、借地権は消滅している。
本件贈与時の本件土地の使用状況等からしても、本件贈与時に本件土地には、借地権は存しない。
国税不服審判所の判断
建物が借地権存続期間満了前に朽廃したときは、 借地権はこれにより消滅するが、 建物が滅失しても借地権は消滅しないとされているところ、本件建物は、本件駐車場設備内の事故を原因として取り壊されたものであり朽廃を原因として滅失したものではないから、平成10年7月に本件建物が滅失したことは、その時点での本件借地権の存続には影響しない。
J社は本件建物が滅失した後本件土地の使用を継続していること、継続して地代を支払っていること及びJ社は建物を再築すべくN社に本件土地の利用計画の策定を依頼していることからすれば、J社としては、本件建物の滅失後も本件借地権を返還することなく、本件土地を引き続き使用及び収益することを予定していたと認められる。
J社は本件借地権を返還していないことから、本件贈与時に本件借地権は消滅していない。
そして、本件借地権が、その発生時から本件贈与時までの間に消滅したとするその他の事由も認められないことからすれば、本件建物が堅固な建物か否か、また、その発生の日が昭和52年8月18日であったのか、あるいは昭和63年であったのかにかかわらず、本件贈与時には本件借地権が存在した。
以上のとおり、本件贈与時に本件土地上には、J社の借地権が存在することは明らかであるから、 評価基本通達 25の定めに従い、本件土地の価額は自用地としての価額から借地権の価額を控除して評価するのが相当である。
原処分庁は、本件土地に対する借地権は本件贈与時には消滅していること及び本件土地は課税時期には更地であったことなどを理由として、 本件土地にはJ社の借地権がないものとして評価すべきである旨主張するが、早ければ昭和52年8月18日 遅くとも昭和63年に発生した本件借地権が、本件贈与時まで存続しており、賃貸人である亡父又は母 Gと賃借人であるJ社の間で、本件土地に係る賃貸借契約の内容が変更された事実も認められないから、本件贈与時に本件土地上にJ社の借地権が存在することは明らかである。したがって、原処分庁の主張には理由がない。
本件においては、本件土地の価額を評価通達等に基づき評価するのが相当であるところ、原処分庁は、本件土地のうち本件a 土地及び本件b 土地につ いてのみ借地権があることを前提として、本件土地を3画地に区分して評価しているが、本件土地の全体に借地権が存在するから、本件土地の価額は、1画地として評価するのが相当である。
コメント
借地権が存するか否かは、土地の価額に影響します。借地権が消滅するのは、建物が朽廃したときです。
本件土地においては、建物が消滅したが、法定更新され、前契約と同一の条件で借地権が設定されたと認められるという。
さらに本贈与時まで本件土地の地代を支払っており、本件土地の相続から本件贈与時までの間に、本件使用に対して何ら異議を述べていないことなどから、本体土地に借地権は存在していたと認められると、審判所は判断していることは、注目すべきことかと思います。
この事案は建物の消滅、地代の支払、建物の朽廃等の判断について学ぶことが多い事例だと思います。