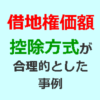底地を取得したつもりが使用貸借と判断された事例

借地権が存在していると思い、底地を取得したつもりが、借地権ではなく、使用貸借と判断された事例 平成14年3月28日 裁決・東京・公開
争点
本件土地の賃貸借は、使用貸借か否か
請求人の主張
父から譲り受けた本件土地の持分部分 (請求人の持分を除いたもの)には、父が所有し、請求人の夫が賃借している建物があること、請求人の所有持分について賃貸借契約を締結し、父が賃貸借料を支払っていることから、請求人が譲り受けたものは底地である。
原処分庁の主張
請求人は、本件各持分は底地の譲受けである旨主張するが、本件各取得日において、本件土地の上には父所有の本件建物が存しており、本件土地の売買の対象となった部分と建物の所有者とは同一人であるから、当該部分に貸借関係が存在していたと解する余地はなく、当該部分は底地とは認められない。
また、請求人と父との間の本件土地の請求人の持分部分に係る本件土地賃貸借契約に基づく賃貸借料は、当該持分部分に係る固定資産税額と同額とされており、当該持分部分に存在する貸借関係は、使用貸借と解するのが相当であり、当該貸借関係の存在は、本件各持分の時価に影響を及ぼす要因とはならない。
したがって、本件土地に賃貸借関係は存在しないので、底地とは認められない。本件土地の賃貸料は固定資産税と同額で使用貸借と解すべきである。売買当日、父所有の建物が存し、賃借人 (婿) が入居中で、 本件土地は貸家建付地である。本件各持分の売買価額は、いずれも本件各持分の時価に比して著しく低い価額と認められるので、 相続税法第7条の規定の適用により、 請求人は、各年分において別表6の 「差額」欄の差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなすのが相当である。
国税不服害所の判断
本件土地の持分の譲渡者と本件建物の所有者とは同一人であるから、同部分に父が借地権を有していたとは認められず、 また、請求人に支払われている賃貸借料は固定資産税額と同額であるから、請求人と父との間の貸借は使用貸借と解すべきである。
そして、本件土地は貸家の用に供されている土地であるから、その価額につき、国税局長が定める財産評価基準書で示されているその土地に係る借地権割合とその貸家の借地権割合との相乗積を当該更地価額に乗じて計算した金額を、その更地価額から控除した価額とすることを不相当とする理由は認められないから、これらを基に本件土地の貸家建付地価額を算定すると、 本件譲受価額は当該貸家建付地価額に比して著しく低い価額の対価と認めるのが相当である。
法令解釈等
※相続税法第7条
相続税法第7条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなす旨規定している。
当該規定は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、法律的には贈与といえないとしても、経済的には対価と時価との差額について実質的に贈与があったと同視することができるため、この経済的実質に着目して、課税の公平の見地から、対価と時価との差額について贈与があったものとみなして贈与税を課税するものであり、当該規定の趣旨にかんがみると、相続税法第7条に規定する低額譲受けによる利益を享受したか否かは、当該財産の時価と譲受けの対価の額との差などを勘案して社会通念に従い判断するのが相当である。
コメント
本件において、本件土地は、父所有の土地上に父所有の建物(居宅)があり、建物所有者である父は娘(請求)の婿と建物賃貸借契約を結んだ。請求人(娘)は父と土地の賃貸契約を結び、その数日後に土地(持分)の売買契約を結んだ。
本件土地の売買契約は平成7年から毎年繰り返し行われた。各年毎に持分の売買であった。請求人は、土地の賃貸借契約を締結しているので本件土地は底地の売買価額であり、底地の適正な価額の1/2を超えているので問題はないではないかと主張するが、土地の賃貸料は固定資産税とほぼ同額であるので、審判所は、本件土地は賃貸借ではなく使用貸借であると判断し、本件土地は底地ではなく貸家建付地であると認めるのが相当とした。
すると貸家建付地としての価額と売買価額との差額は、相続税法第7条の著しく低い価額の対価であると認めるのが相当と指摘した。即ち、売買価格/貸家建付地の比率は29.1%で、貸家建付地価額1/2にも満たないことが分かりました 。
権利関係が複雑になればなるほど、状況把握を如何にすばやくするか、見落としはないか注意を払い、売買契約を締結する必要があります。
貸家建付地とは、建付地上の建物が賃貸されている場合のその宅地をいいます。
借家件の付着している場合、借家法(借地借家法の制約は建物のみならず、その敷地にも及び、一般的に建地の価額はより低くなる傾向があります。