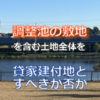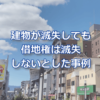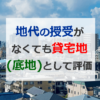相続人(親子間)の居住用建物が存する敷地は、自用地として評価した事例

争点
相続により取得した土地は、借地権の目的となっている土地(底地)か否か
請求人の主張
本件土地上に請求人の自宅を建築する際に、本件被相続人と請求人は借地契約を締結し、これに基づき地代を支払っていたことなどから、本件宅地の借地権を請求人が有しており、本件土地は底地である。
原処分庁の主張
本件土地に借地権は存在せず、本件土地は自用地である。
本件被相続人及びFは、本件土地に借地法の適用がある借地権を設定することを目的として本件借地契約書を作成したものではなく、将来発生する本件被相続人に係る相続税を軽減することを目的として本件借地契約書を作成したと認めるのが相当であるから、本件地代は、本件被相続人の相続税を軽減することを目的として支払われた金員にすぎず、 Fが本件土地を利用することについての対価ではない。
したがって、本件土地は、本件土地の本件被相続人とFとの間の貸借関係は、使用貸借と解するのが相当である。
以上により、本件土地は、底地とは認められず自用地であると認められる。
審判所の判断
請求人らは、Fが本件相続開始日に本件土地の借地権を有していた旨主張するので、以下検討する。
本件地代が本件土地使用の対価であるとは認め難く、本件被相続人とFの本件土地の貸借は、親子という特殊関係に基づく使用貸借であって、賃貸借ではないと解すべきであるから、この点に関する請求人らの主張には理由がない。
なお、請求人は、本件被相続人は本件地代について毎年所得税の確定申告を行っていたのだから、本件土地は底地である旨主張する。
しかしながら、本件被相続人が本件地代について所得税の確定申告をしていたからといって、本件土地が底地となるものではないから、この点に関する請求人らの主張には理由がない。
また、請求人は、本件地代の額は本件土地に係る固定資産税等相当額を上回っているのであるから、本件通達の定めにより、本件土地は底地である旨主張する。
しかしながら、本件通達は、借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるものは、使用貸借に該当し、その土地の使用権の価額は零として取り扱う旨を定めたものであって、公租公課を上回る金額の授受があれば、直ちにその土地の貸借関係が賃貸借となると定めたものとは認められないから、この点に関する請求人らの主張にも理由がない。 よって、本件土地は自用地である。
コメント
請求人は、本件相続税の計算に当たり、本件被相続人の所有する本件土地に請求人の 自宅を昭和52年に建築する際に、本件被相続人と請求人は借地契約を締結し、これに基づき地代を支払っていたことなどから、 本件宅地の借地権を請求人が有しており、本件土地は底地である旨主張する。 しかしながら、両者の本件土地の貸借は、 権利金の授受がないこと、地代の額が近隣の相場の約39%であること、 地代の額を相当に上回る生活費の支払や現金の贈与が本件被相続人から請求人及びその家族に対してなされていることなどから、親子という特殊関係に基づく使用貸借であって、賃貸借でないと解すべきであり、本件土地は自用地である。
本件土地の使用は、次のような理由で親子という特殊な関係に基づく使用貸借であり、賃貸借ではないと解すべきであると、審判所は判断しました。
②被相続人と相続人は、母子の関係であること
③被相続人と相続人は権利金の授受の慣行のある地域に所在するも、権利金を支払っていないこと
④本件地代の額は、固定資産税等の額の1.5倍程度であり、近隣の地代の相場の39% の水準であること
⑤被相続人は、地代の額を上回る生活費を支払を行っていたこと
以上から、本件地代が本件土地の対価とは認め難く、本件土地の貸借は、親子という特殊関係による使用貸借であると、審判所は判断しました。
地代の額については、一般的に固定資産税等の3倍程度が一般的かと思います。